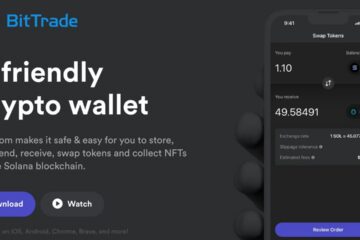【ステーブルコインの買い方ガイド】日本国内での購入方法や使い方を解説

ステーブルコインとは、法定通貨などに価値を連動させることで価格変動を抑えた暗号資産(仮想通貨)の総称です。
米ドルに連動するテザー(USDT)やUSDコイン(USDC)などのステーブルコインは、国際送金のための決済手段として既に活用されており、日本国内においても法整備が進められたことで様々な企業によるステーブルコインの発行や利用が促進されています。
この記事では、ステーブルコインの基本的な情報と具体的な買い方、使い方について紹介していきます。
ステーブルコインとは?安定通貨として注目される理由
ステーブルコインは法定通貨やその他の資産と価値を連動させる仕組みを持つ暗号資産(仮想通貨)の総称として使われており、米ドルに連動するテザー(USDT)や金価格に連動するジパングコイン(ZPG)など様々な種類のステーブルコインが発行されています。
価格が安定しているという特徴から、日常的な決済用途や暗号資産(仮想通貨)としてDeFi(分散型金融)などへシームレスにアクセスすることが可能です。特に送金を行う際のスピードや手数料の面で従来の金融システムよりも優れていることから、グローバルな資金移動を効率化する手段として需要が拡大しています。
ステーブルコインのメリット
価格安定性
ステーブルコインは価格が法定通貨やその他の資産に連動するため、ビットコイン(BTC)などの一般的な暗号資産(仮想通貨)と比較して価格が安定しており、送金や決済に利用しやすい特徴を持っています。
リスクヘッジ
暗号資産(仮想通貨)の相場状況に関わらずに安定した価値を保存することが可能なため、リスクヘッジの手段として利用することができます。また、一部のステーブルコインは株式や債券との値動きの相関が低い金などの貴金属価格と連動するものがあるため、様々な局面で活用することができます。
高速・低コスト
銀行などの既存金融の送金サービスと比較して、高速かつ低コストで利用することが可能です。また、自身のプライベートウォレットから相手のウォレットへ直接送金を行うことで面倒な手続きを踏まずに簡単に利用することができます。

ステーブルコインのデメリット・注意点
ステーブルコインは価格の安定した利用しやすい暗号資産(仮想通貨)と紹介しましたが、併せて考えなければいけないのがデメリットです。
ステーブルコインは銀行預金や現金などと異なり、暗号資産(仮想通貨)としてデジタル上で保有・取引を行います。そのため、ウォレットの破損やパスワードを忘れてしまった場合には資産を失ってしまう可能性があります。
また、送金の際に誤ったウォレットアドレスを入力してしまった場合にも二度と資産を取り戻せなくなってしまうので操作には注意が必要となります。
利用するDApps(分散型アプリ)やウォレットによってはハッキングのリスクも考慮する必要があるので、他の暗号資産(仮想通貨)と同様に安全管理に気を付けて利用しましょう。
ステーブルコインの仕組みと4つの分類
ステーブルコインは裏付け資産やアルゴリズムによって安定した価格が保たれています。
ここでは、それぞれのステーブルコインの仕組みを大きく4つに分けて紹介します。
法定通貨担保型
法定通貨担保型は、米ドルなどの法定通貨を準備金として保有し、その額に応じたステーブルコインを発行する仕組みです。
多くの場合、常に1コイン=1通貨単位の価値を持つことを目指しており、交換レートなどを気にせずに利用することができます。発行体が保有・管理する資金を定期的に監査することでステーブルコインの安全性や信頼性を高めるのもの存在します。
暗号資産(仮想通貨)担保型
暗号資産(仮想通貨)担保型は、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの暗号資産(仮想通貨)を裏付け資産としています。
多くの場合は流通するステーブルコインの価値以上の暗号資産(仮想通貨)を担保としていますが、担保となる暗号資産(仮想通貨)の価格が急激に下落した場合にはペッグが外れてしまうことや、スマートコントラクトによってステーブルコインがバーン(焼却)されてしまうので注意が必要です。
コモディティ担保型
コモディティ担保型のステーブルコインは貴金属などのコモディティ資産を担保として発行されます。
担保となるコモディティ商品の価格に連動するため、ステーブルコインでありながら投資目的にも利用されています。
アルゴリズム型
アルゴリズム型は、担保資産を持たない代わりに発行量の調整や買い戻しを行うスマートコントラクトの仕組みによって価格を安定させる方式です。
需要が高まれば新規トークンを発行し、需要が落ち込めばトークンをバーン(焼却)するなどの手法で価格を安定させています。市場の急激な変動や需要の変化により、発行やバーン(焼却)が追い付かなくなった際にはステーブルコインの価値が大きく変動する場合もあり、裏付け資産を持たないことから価値が0になる可能性もあります。

代表的なステーブルコイン一覧
20214年に米ドルと連動するテザー(USDT)が発行されて以降、さまざまな国の法定通貨やコモディティ商品価格と連動するステーブルコインが誕生しています。
ここでは、取引量や利用者の多い主要なステーブルコインや、日本国内で発行・流通するステーブルコインを個別に紹介していきます。
テザー(USDT)
テザー(USDT)は2014年に米ドル連動型のステーブルコインとして発行され、ステーブルコインとして最大の時価総額を持つ暗号資産(仮想通貨)です。海外の大型取引所やDeFi(分散型金融)で多く取引されており、他の暗号資産(仮想通貨)との交換をスムーズに行うことができます。
一部の国や地域ではテザー(USDT)を法定通貨として、民間企業による決済受付や納税で利用することが可能です。
テザー(USDT)について詳しくはこちらをご覧ください。
USDコイン(USDC)
USDコイン(USDC)は、Circle社によって発行される米ドル連動型のステーブルコインです。
裏付け資産となる米ドルの準備金残高を監査報告により公開しており、高い透明性によって支持を集めています。
日本国内の取引所でも取扱われており、身近に利用することができるステーブルコインです。
USDコイン(USDC)について詳しくはこちらをご覧ください。
ダイ/USDスタンダードトークン(DAI/USDS)
ダイ/USDスタンダードトークン(DAI/USDS)は、暗号資産(仮想通貨)担保型のステーブルコインで、MakerDAOによって発行・管理が行われています。
ダイ(DAI)として発行されていましたが、2025年にMakerDAOのガバナンス投票によりUSDスタンダードトークン(USDS)に名称を変更しました。
JPYコイン(JPYC)
JPYコイン(JPYC)は日本企業のJPYC株式会社が発行を予定する日本円連動型のステーブルコインです。
日本国内の法律に準拠したステーブルコインとして、暗号資産(仮想通貨)とは区別された「電子決済手段」として運用が行われています。
JPYコイン(JPYC)について詳しくはこちらをご覧ください。
ジパングコイン(ZPG)
ジパングコイン(ZPG)は金価格に連動するステーブルコインです。
発行・管理は三井物産デジタルコモディティーズが行っており、小口から取引可能なインフレヘッジ機能を持った金の代替商品として取引されています。
ジパングコイン(ZPG)について詳しくはこちらをご覧ください。
ステーブルコインの買い方と購入手順
日本国内でステーブルコインを入手するには、暗号資産交換業の資格を持つ業者を通じて取引するのが一般的です。
取引所を選ぶ際にはステーブルコインの取扱いがあるか以外にも、セキュリティ対策や手数料体系を総合的に比較しましょう。
BitTrade(ビットトレード)では、サービス開始以来ハッキング0件で万全のセキュリティ対策を行っており、口座開設にかかる手数料や販売所での取引手数料が無料でご利用いただけます。
ここでは、BitTrade(ビットトレード)を使ってステーブルコインを購入するための方法を紹介していきます。
暗号資産取引所での口座開設
最初にBitTrade(ビットトレード)の口座を開設します。
以下のボタンから口座開設フォームに進み、メールアドレスの登録を行ってください。
登録が完了後、本人確認の案内が届きます。スマートフォンで本人確認が完結する「かんたん本人認証」を利用することで、最短即日の取引開始が可能です。
かんたん本人認証の方法は以下の動画で紹介しています。
購入代金(日本円)の入金
口座開設後、ステーブルコインを購入するための日本円を入金します。
BitTrade(ビットトレード)では「銀行振込」「クイック入金」「ペイジー入金」「コンビニ入金」の4つの入金方法をご利用いただくことができます。
ステーブルコインと日本円の取引
日本円の入金がBitTrade(ビットトレード)の口座に反映されると、ステーブルコインを購入することが可能になります。
BitTrade(ビットトレード)で取扱っているステーブルコインは「ダイ(DAI)」と「ジパングコイン(ZPG)」のため、取引画面からこの2銘柄のうち取引したいステーブルコインを選択してください。注文画面で数量や注文内容を入力して確定ボタンを押すことで取引が可能です。
購入後は口座内にステーブルコインが残高として表示され、投資として保有することや、外部へ出勤して自身のウォレットなどで運用することができます。
ステーブルコインの使い方
保有するステーブルコインは、決済やブロックチェーン上での運用などさまざまな使い方があります。
ここではステーブルコインの活用方法として、「決済」「資産の保全」「投資・運用」の3つを紹介していきます。
決済手段
ステーブルコインは、安定した価値を高速かつ低コストで送受金可能なため、決済手段として広く活用されています。
海外ではコンビニチェーンや自動車メーカーがステーブルコインによる支払いを受け付けており、日本国内でも一部のオンラインショッピングなどで受け入れが始まっています。
ブロックチェーンにより銀行や決済業者を必要としないため、中間手数料の削減やリアルタイムに近い決済が特徴です。
資産の保全
一般的にボラティリティの大きな暗号資産(仮想通貨)の市場では、一時的にステーブルコインに資産を交換することで資産価値を一定に保全することが可能になります。
ステーブルコインは暗号資産(仮想通貨)の相場状況に左右されない価値を保つことができるため、リスク管理の一環として活用されています。
投資・運用
DeFi(分散型金融)や一部の取引所では、ステーブルコインを預け入れて金利を得るレンディングサービスやステーキング機能を提供しています。
一般的に銀行預金よりも高い利回りでステーブルコインを貸し出すことが可能ですが、投資として行う際のリスクとして、ハッキングによる資産の流出やステーキングのスラッシングによる資産の没収があることを意識しましょう。
ステーブルコインに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、ステーブルコインをこれから購入する際や利用する際に気になる点をFAQ形式で紹介していきます。
日本国内でステーブルコインを購入するには?
ステーブルコインの買い方は、暗号資産交換所で購入するのが一般的です。中には、ステーブルコインを取扱っていない業者もあるため、各交換所の取扱銘柄を確認することが必要です。
BitTrade(ビットトレード)の販売所では、24時間365日(メンテナンス時間を除く)、ステーブルコインのダイ(DAI)とジパングコイン(ZPG)を取引手数料無料で購入することが可能です。
ステーブルコインの価格は常に安定しているの?
ステーブルコインの多くは裏付けとなる資産を保有しているため、基本的には安定した価格で流通していますが、急激な需給の変化やアルゴリズムの破綻により、ステーブルコインの価格が変動する場合もあります。
ステーブルコインの関連記事
※本ページは、情報提供のみを目的としており、暗号資産関連取引の勧誘または推奨を目的としたものではございません。売買等に関する最終判断はお客様ご自身で行ってください。
※当社は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではなく、お客さまがこの情報もしくは内容をご利用されたことにより生じた損失に関し一切責任を負うものではありません。
※本ページにおける取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツは一般的な情報提供を目的に作成されています。また、当コンテンツはあくまでもお客様の私的利用のみのために当社が提供しているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。
※当社は予告なしに、ウェブサイトに掲載されている情報を変更することがあります。